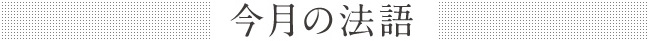
「何か面白いことはないか」私は、人にこう尋ねることがよくある。何を面白いと感じるかは、人それぞれだろうが、それを共有できた時は楽しい。
先日、NHKのテレビで教科書を黒く塗りつぶしているシーンが放映されていた。今まで幾度となく見てきた戦後の一場面である。その時、少年少女だった人は、どういう気持ちで、きのうまで先生が教えて下さったことを墨で塗りつぶしたのだろう。今まで真面目に、教わって、習って経験してきたことが、全部ウソだったと言われたらどうだろう。騙された、裏切られた、もう何も信じられないと叫ぶだろうか。
甲本ヒロトさんは、こんな詩をつくっている。
見てきた物や聞いた事
いままで覚えた全部
でたらめだったら面白い
そんな気持ちわかるでしょう
答えはきっと 奥の方
心のずっと奥の方
涙はそこから やって来る
心のずっと奥の方
(『情熱の薔薇』より抜粋)
甲本さんは、「でたらめ」だったら「面白い」と言っている。なぜ、「面白い」と感じたのだろうか。その答えは、どうやら心の奥にあるらしい。これは面白いと私は思うのだが、はたして、親鸞聖人におかれては何を、「面白い」と感じておられただろうか。
末法の世に真の仏道を求めた聖人は比叡山の門に入り二十年間修行をされた。この世でのさとりを求めて、教えられた聖者の道を真剣に進んで行った。しかし、その道は出口のない迷路のようであった。絶望の深い悲しみの中で、法然上人に出遇い、「ただ念仏」の声を聞く。それは暗闇を破る燈火として、心の奥底から照らし出された。ごまかす必要のない正直な道を知らされる。今まで信じていた自分の思いが、妄念妄執のでたらめであったことに気付く。自力の心がひるがえり、常識を疑うことができた。しがみついていたその手が剥がされ、落ちていった底のまた底から、仏は大いなる悲しみをもって起ちあがり、妄念でできあがった自分をそのまま、摂め取ってくださった。
「雑行を棄て本願に帰す」親鸞聖人は、悲喜の涙とともに念仏を申された。
本当の面白さとは何だろう。そこに笑いがともなうとするなら、決して哄笑ではなく、微笑みとして現れると思う。悲しみの奥底から涙とともにこぼれてくる微笑である。それは自分の日ごろの心が向き直り、歩むべき方向の道しるべが見出された喜びであろう。これを廻心という。妄念の凡夫である人間だからこそ、悲しみの中で仏と出遇い廻心する。人間だけにそれが起こる。凡夫の自覚を生きられた親鸞聖人は、そんな人間そのものを、「面白い」と感じて歩いて行かれたのではないかと私は思っている。
江戸川本坊 大空

