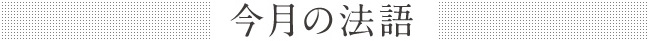
「国宝とは何者ぞ、宝とは道心なリ。 道心ある人を名づけて国宝と為(な)す。」これは伝教大師(最 澄》の著した『山家学生式(さんげがくしょうしき)』の冒頭部分です。国宝とは何でしょうか。ここにいう宝とは、仏道を求め、道を修めようとする心です。その心ある人を国宝と名づけています。同様に斉の威王は「径寸十枚(直径が一寸もある宝石が十個)は国宝とは言えません。一隅を照らす人こそ国宝です」 と言っています。さらに伝教大師は、釈迦の教えの中に、僧侶には「小乗の類」と「大乗の類」の 二種類あると言い、「道心ある仏、弟子、即ちこれは大乗の類なり」と言われました。また、『末灯鈔(まっとうしょう)』には、「浄土真宗は大乗の中の至極なり」と、我々の宗祖である親鸞聖人のお言葉が記されています。
親鸞聖人は一一八一(養和元)年九歳で得度されています。それは道を求めるという出発点です。その頃は大変な飢饉が起こったそうで、京都の加茂川が死体でいっばいに溢れたそうです。その時の様子を『方丈記(ほうじょうき)』には、「親子あるものは、定まれる事にて、親ぞ先たちける。又母の命つきたるを不知(しらず)して、いとけなき子の、なほ乳をすひつゝ臥せるなどもありけり。(中略)すべて四万二千三百余りなんありける(『方丈記』鴨長明 著)と、当時の悲惨な光景が如実に記されています。普通、食べ物が無い時でしたら、小さな弱い子どもから先に死んでいくものだと思いますが、「親ぞ先立ちける」とありますから、子供よりも先に親が死んで行ったのです。それは、親は自分が食べるよりも先に、子どもに食べさせたからです。そして自分は飢え死にする。子どもに何とか生き伸びてほしいから、自分は食べずに子どもに全部与える。だから親が先に死んでしまうのです。そして、幼児は、お母さんが死んでしまったことも知らず、けなげにもなお、お母さんの乳を吸っているというのです。その数、「四万二千三百余り」です。これは一ケ月間のことだとあります。四万二千三百人余り」が亡くなっているのです。実は、親鸞聖人が得度した頃は、こういう世の中だったのです。まさに地獄そのものです。親鸞聖人の道を求める出発点には、こういう情景が、その幼い眼(まなこ)に、しっかりと焼き付けられていたのだと思います。
「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり」
これは、親鸞聖人が『唯信鈔(ゆいしんしょう)文意(もんい)』に書かれたお言葉です。「いし・かわら・つぶて」とは、その日の生活もままならない、当時の身分制度のうえで最下層とされたような人々や、善根を積むどころか、生きるためには、悪事さえもあえてしなくてはならない一般民衆の人たちのことです。親鸞聖人はそういう人たちと共に「われら」として生きられたのです。親鸞聖人は、自分一人の努力で親鸞聖人になられたのではなく、「いし・かわら・つぶてのごとくなる」人たち、そのような親鸞聖人をとりまく無数の人たちが浄土を課題とする親鸞聖人という人を生んでくださったのだと思います。国宝とは、まさにこのような人たちをいうのではないでしょうか。
そのことが、私に、仏道を求めようとする心を起こさせ、歩むべき道を照らし示してくださっているのだと思います。
證大寺 森林公園支坊 佐治敬順

