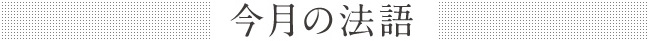
十二月の法語は、安田理深(やすだりじん)先生の言葉に聞いて行きます。
さて、皆様方はこの言葉を聞かれてどの様に感じましたでしょうか。先生は個人的な救いを否定され、公の救いを問題にされています。それが「仕事を与えられること」です。それではこの「仕事」とは何を言うのでしょうか。
先生のお弟子の宮城顗(みやぎしずか)先生はある時「ねんごろ」と言う言葉に注目され、色々な辞書で調べられました。その内容は『人と生まれて』と題して出版されています。先生は「ねんごろ」と言う言葉の語源は「ねもころ」と言う字から転じた言葉であると言われています。「ねもころ」の「ね」は「根」と「如(もころ)」と言う字を書いて「ねんごろ」と読ませます。その意味は「根もからみつくほどに」と言う意味で、木がお互いに根を絡みつけ合っていて、その根を切り離す事は出来ない、別々にならない。一つになって生きると言う意味であると言われています。私共人間は本来、このねんごろの様な歴史を持った存在なのです。
さて、その人間と言う字ですが、先ず「人」を書きます。これはお互いが支え合っている事です。そして次の「間」は間柄で関係です。ですから人間とは関係の中で、お互いが支え合い、助け合っているものなのです。その関係が人と人と、又、人と自然との関係です。この関係が無くなったら人間で無くなります。しかしながらその関係を壊す本(もと)になっているものがあります。それが自分の思いに執着する事です。私共はその事から離れられずに、一人ひとりが孤立し、心通じる事無く、又、自然を壊しながら、バラバラに生きています。先生はその様な自分中心の思いが破れたところに「公の救い」があると教えています。私共はその思いに行き詰まると、楽になりたい為に、神仏の力に頼る者や、自らのいのちを絶つ人などがいるのです。しかし行き詰まりは、念仏の教えを聞く良いきっかけとなります。そして教えを聞いて行くと道理を知り、今まで道理に背きながらも、本当の自分に成らずにはおれない意欲が湧き出て来ます。その意欲は人と人、人と自然との関係を回復させ、又、他の者にも気付かせて、心通じ合って生きて行く国土(社会)を開く意欲です。その意欲こそ私共が気付かずにいた本能です。それを教えからいただくのです。その意欲を「願い」と言い、その願いを背負って、他の者と共に国土(社会)を開く歩みを先生は「仕事を与えられること」と言われていると思います。
加藤 順節

