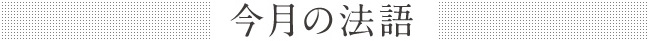
今月のともしび掲示板は鴨長明が著した『方丈記』の一説です。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀(よど)みに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世の中にある人と、栖(すみか)とまたかくのごとし」の冒頭で知られるように『方丈記』に一貫しているのは「無常観」です。
仏教の根本思想に諸行無常とあります。すべてのものは常住ならざるもので、常に生滅変化して、しばらくもやむことがないということです。
私たちは諸行無常と聞くとどうしても、そこに死を連想し、衰え滅していく寂しさ、わびしさを感じるといった「滅」の側面にのみ心を奪われがちです。しかしそれは無常の一つの意味でしかありません。「滅」と同時にあるのは「生」です。諸行は無常だからこそ生まれるということが起こります。生まれた赤ん坊がいつまでも生まれたままでなく成長していくことが起こるのも、苦しみや悲しみのどん底にある人がそこから脱して、また力強く立ち上がって行けるのも、諸行は無常であるからに他なりません。 無常は消滅ではなく生―滅、そして滅―生なのです。
そのような常に変化し続ける世界であるにもかかわらず、この世を終(つい)の棲家(すみか)のごとく執着して安住を求める私たちの有り様を長明は「仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる」と記しています。聖徳太子は「世間虚仮」と言われ、親鸞聖人は「そらごとたわごと、まことあることなき」と決定づけられました。これは人間を否定された言葉ではありません。頼りにならないものを頼りにして苦しみ迷う人間が根源的に抱えている愚かさを、自らの苦悩を通して知らされた真実の言葉であったと思います。そしてそれと同時に先駆けて聞こえてきたのは、蓮胤(長明)は「不詳の阿弥陀仏、両三遍申して、やみぬ」であり、太子においては「唯仏是真」。聖人は「ただ念仏のみぞまことにておわします」という真言でした。 それは真実によって無常が知らされ、その無常の中で常住の真実に出遇えた感動であったと思います。 私にとって真実は、自らも無常の身であることを知らされた悲しさ、虚しさの内より起こってくる如来の大悲だと思うのです。 「久しくとどまりたるためし」のない無常の身にあって、そこにこそ真実を与えようとする如来の慈悲が私の心を響かせるのだと思います。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という変転し静止することのない無常の中で、寂しく、わびしい心が取り留めもなく起こってくる。だが、そのときこそ如来との出遇いが生まれ起こっている契機だと私は受けとめています。有限である我を、 朝に死に、夕に生るゝ我ら、と確かにいただけるところに、無常のまま独り歩んで行ける道が無限に開かれていくのではないかと思います。
江戸川本坊 大空

