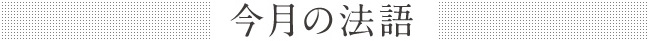
竹中先生は京都にある大谷専修学院の元学院長である。
一般的には『摂取不捨』とは「摂め取って捨てない」という意味だが、私たち学院生にわかりやすく伝えるためにおっしゃられた言葉が「えらばず・きらわず・みすてず」である。
私たちの生活の中で「えらばず・きらわず・みすてず」の実践はとても困難だ。何故ならば、何処かしらで、人や物を選んだり、嫌ったり、見捨てて生きているからだ。口に出したとしても、出さなかったとしても、自分の経験や行動、思いの中では「えらばず・きらはず・みすてず」ということは成り立たないのだ。それは、こっちを立てると、あっちが立たないといった具合にいつもどちらかを選んでいるからだ。
思いの中や考えの中では到底、その疑問に対する答えと言うものは出てこないのではないだろうか。何故ならば、人の考えを超えたものだからであり、それは、阿弥陀如来の大慈大悲の心だからだ。阿弥陀如来は生きとし生ける、悩み苦しむ一切の衆生を救いたいと願われた。その心というものが「えらばず・きらはず・みすてず」なのだ。誰一人としてもらすこともなく、皆、共に往生して欲しいという願いがここには託されているのだ。そして、阿弥陀如来は四十八の願いを建てて下さった。この願いというものは、私たちを見捨てないという宣言でもあるのだ。どうしても選んだり、嫌ったり、見捨てたりしてしまう、そう言うことでしか生きていけない私たちに対しての絶対的な救いなのである。
私たちはこの「えらばず・きらわず・みすてず」という阿弥陀如来の心を、実は本質的には持っているのかもしれないのだ。皆、選んだり、嫌ったり、見捨てたりした時に、「これで良かったのか?どうしてあの時こういう判断をしたのだろう?」と後悔したり、悩んだりしないだろうか。「えらばず・きらわず・みすてず」を出来ないでいる私たちに対して、阿弥陀如来は心の方から呼びかけてきているのだ。
心の呼びかけに目を向けられないでいるのは日々の生活の中での自分の思いだ。時々気がついたとしても、ずっとそちらに目を向けながら生きていくと言う事が難しく、気持ちの上では応えていきたいと感じるのだが、いつの間にか目を外してしまっている。けれども、心の方からの呼びかけに少しでも応えられた時、阿弥陀如来からの呼びかけというものにも、少しばかり気づく事ができるのではなかろうか感じるのだ。私自身も自分の内面の呼びかけを大切に、応えて生きていけたらと感じている。
森林公園支坊 藤場善寛

