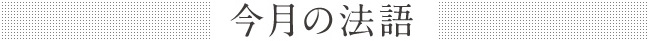
「青は藍(あい)より出でて藍より青し」ということわざがあります。元来、青色は、植物の藍から染料を取ってつくられました。その青色がもともとの藍より青く美しくなることから、弟子が師匠よりぬきんでて学識や技量がすぐれることをいいます。「氷は水より出でて水より寒し」というのも同じ意味を表しています。いずれも『荀子』のことばです。
曽我量深先生は、自ら師匠をみいだし、生涯仏弟子として教えを聞き続けられ、今を生きる私たちに親鸞聖人のおことばを託してくださった真宗大谷派の僧侶です。
先生は、「学問というものはまず師匠をうやまうところにはじまる」「学校にはいったからには一生涯教えをうける先生をみいだすことにつきる」と言われました。「なにも師匠は弟子よりえらいわけではない。青は藍よりいでて藍より青し、弟子は先生よりえらくなるのがほんとうである。しかし、えらくなったとて師は師であり、弟子は弟子である。弟子は師匠より何段えらくなったとしても、だいじなことになると師に相談をかけ、師より証明していただく。それだけのことのできる人は尊敬すべき人である」と曽我先生は教えてくださっています。
親鸞聖人にとって師匠は、法然上人です。聖人は、法然上人以上にお念仏の教えを深め、より純化させたのかもしれません。しかし、聖人は生涯いつでも法然上人を「よきひと」として念じておられました。そのような聖人のおすがたを曽我先生は、「青年親鸞」と称されました。
それは、いつでもお師匠さまを念じるところに若い心にかえり、八十になっても九十になっても教えをうけた若々しい精神は失われないということです。だから「師匠をもてる人は、じつにいかに年をとっても青年」であり、「師を念ずればいつも師匠はあらわれる」のだそうです。
私はそのような師匠をみいだすことができるでしょうか。曽我先生は、「おことばを聞く、文字を読んではならない」と言われます。「その人のことばを聞け」「おことば自身の中に意味がちゃんとあるから、そのおことばを聞きさえすればよい」とご教示してくださっています。私は、「ことばを文字にして頭で考えているからわからない」と指摘されました。
親鸞聖人は、お聖教の文字に仏のじきじきのことばをみいだし、生きたおことばを頭をさげて聞かれたといいます。そのような、学び方の態度に、師をみいだし、師からみいだされるということがおこるのでしょうか。
曽我先生は、よき師匠のところに行くと、人間は赤子のようにすなおになるとしめされ、「たとい師匠はなくとも、自分の親、世の中からみれば平々凡々たる親であるが、常に親を念ずるということになれば、たとい自分は立身出世しても、子供のように無我の心を失わない」と言われました。
一生涯師匠をもち、親をもつ。赤子のようにすなおになって、いつまでも若々しい心をもつ大切さを先生は伝えてくださっています。「悪は悪のままで、どんな悪でも悪を悪と知るところに悪のままで明るい世界にはいりうる。自分がえらいものと思うと世の中が暗くなる」
このような文字にまでなってくださった曽我先生のおことばに頭をさげ、すなおに聞かせていただくところに、本当に尊いことへの出遇いの世界が開けていくのだと思います。
江戸川本坊 大空
(参考文献 曽我量深『歎異抄聴記』東本願寺出版部)

