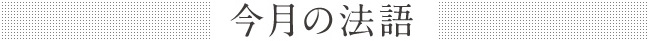
源左(げんざ)は天保十三年(一八四二年)四月十八日に鳥取県東部の因幡(いなば)に生まれ、妙好人(みょうこうにん)と呼ばれた念仏者です。そして念仏の教えを言葉に残して、昭和五年二月二十日に八十九歳で浄土に還りました。
さて、源左は十八歳で父親と死別しました。父親は、「おらが死んだら親様をたのめ」と遺言しますが、源左は意味が分からずにお手次の本願寺派願正寺(がんしょうじ)の住職から念仏の教えを聞かれます。
そして三十歳の夏の日にデン(鳥取県山根の方言で牛のこと)を連れて山へ草刈に行きました。そして山から下りる時に刈った草を束ねてデンの背中に載せようとしますが、「デンも苦しいだろうから」と、自ら草を担いで下ります。しかし途中で重くて歩けなくなり、デンの背中に載せた時に”すとん”と楽に成ったそうです。源左はこの時に遺言の意味を知りました。そのことをこの様に話しています。
「ここがお他力か、わがはからいではいけんわい、お慈悲もこの通りだと気付いてなあ。デンに知らせてもろうてなあ。デンはおらあが善知識(ぜんぢしき)だがやあ。この朝長い間の夜明けをさせてもらっただいなあ。おらデンめに、ええご縁をもらってやあ。帰りにゃ親様のご恩を思わせてもらいながら戻っただいなあ」(『妙好人を語る』NHK出版)と言われています。
源左は住職を訪ねて喜びを確認すると、「源左そこだ」と言われて、この日を機縁に心配事が無くなりました。源左が気付いたことは宿業の身です。この業苦に苦悩する源左を助ける如来のはたらきに背を向けていた我が身の愚かさを知ったのです。
父親の遺言の意味は、「自分の思い通りに成らない身を如来に任せて如来の願いに生きよ」ということでした。
源左はこれを機に、「ようこそ、ようこそ、さてもさても」の言葉が口癖に成りました。このようこそとは因幡の地方の方言で、「ありがとう」です。
ですから、「阿弥陀如来がこの源左を助けるぞと良く誓って下さった。ありがとう、ありがとう」という意味です。このことが転じて源左の生き方が、「ようこそ、ようこそ」と、境遇を受け入れる、「包容」の姿勢に転じて行きました。
そして源左の二人の子供は若くして亡くなります。源左にとって尤も悲しい境遇を受け入れることになります。そして長男竹蔵さんを亡くした時にはこの様に語られました。
「竹はなあ、この世のきりかけ(自分に与えらた分)を済ましてお浄土へ参らしてもらったわいの。おらあはとろい(のろい)でいちばん後から戸をたてて(この世の戸締りをして、つまりこの世で自分のやるべきことをして)、お浄土へ参らせてもらうだがよう」と言われます。住職は源左を心配して、「仏のお慈悲に疑いや不足が起らないか」と聞けば、「ありがとうござんす。御院家(ごいんげ)住職さん、如来さんからのご催促でござんすわいなあ。」と答えています。
『妙好人を語る』よりこの「ご催促」とは、「源左よ、諸行無常の原点に立て。今、いのちが源左を生きている」との如来の激励だと思います。その激励に「勇(いさみ)」が生じます。
この勇が源左が取り組むべき課題と成って、今日一日をいきいきと生かせるのです。それが先程の「この世で自分のやるべきことをして」の本意だと思います。私はこの言葉に仏教終活の真意を感じてなりません。
船橋支坊・加藤順節

