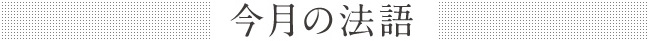
今から二十五年程前になろうか中学生だった私は、当時流行っていたトランジスターラジオで深夜放送をよく聞いていた。私の生まれ育った九州福岡は深夜ともなると殆どの番組が終了し、雑音の中、聞こえてくるのは、韓国からのハングル語放送だった。その中で唯一日本語で楽しませてくれたのが朝五時までやっていた某深夜放送だ。曜日ごとパーソナリティーがきまっており、その中でも異色だったのが中島みゆき氏だった。その語りは妙に明るく多少お下品もありつつも、どこか憂いがあった。当時からテレビに出る方ではなかったので、レコードのジャケットを見てその美人さとラジオでのギャップに驚いたのを今でも憶えている。そのみゆき氏の放送の中で流れていた彼女の歌『傾斜』のフレーズが今号の言葉だ。
≪傾斜一〇度の坂道を腰の曲がった老婆が少しずつのぼってゆく
紫色の風呂敷包みはまた少しまた少し重くなったようだ
彼女の自慢だった足はうすい草履の上で横すべり横すべり
のぼれどものぼれどもどこへも着きはしない、そんな気がしてくるようだ
冬から春へと坂を降り 夏から夜へと坂を降り 愛から冬へと人づたい
のぼりの傾斜はけわしくなるばかり
♪としをとるのはステキなことです
そうじゃないですか
忘れっぽいのはステキなことです
そうじゃないですか
悲しい記憶の数ばかり 飽和の量より増えたなら忘れるよりほかないじゃありませんか≫
皆さんはどう感じるだろうか。この曲は前半はとてつもなく暗く重く、うら悲しいのである。ところが突然、後半、「としをとるのは・・」からいきなり明るくなる。何かが吹っ切れたかのごとく、最後までいっきにのぼりつめていく。当時の私はこの曲と詩のイメージから、老いや死といった先の見えない漠然とした恐怖を感じながらも、後半の開き直りともとれる異様な盛り上がりに不思議な安堵感が得られ爽快な気分にさせられたものである。
それから二十数年がたち現在ありがたく仏法を聞かせていただく身となってから不思議とこの歌詞が頭に流れてくるのだ。釈尊は六年間の苦行を捨て、お悟りをひらく。親鸞は二十年間の叡山での壮絶な修行では悟れず山を捨て、念仏の教えに出遇って回心する。自力の極みを尽くし沸騰し即ち爆発する。そこに仏の本願力のみぞ、まことと知らされるのではないか。 「法を聞くということは、何かをつかむのではない。しがみついている何かがはがされていく道だ。」と先達に聞いた。私の救われる道は、それよりほかないということだろう。
最後に、絶対他力の大道を歩まれた清沢満之先生の信心をいただきたいと思います。 【言葉を慎まねばならぬ、行いを正しくせねばならぬ、法律を犯してはならぬ、道徳をやぶりてはならぬ、礼儀に違ふてはならぬ、作法を乱してはならぬ、自己に対する義務、他人に対する義務、家庭に於ける義務、社会に於ける義務、親に対する義務、君に対する義務、夫に対する義務、妻に対する義務、兄弟に対する義務、朋友に対する義務、善人に対する義務、悪人に対する義務、長者に対する義務、幼者に対する義務等、いわゆる人倫道徳の教より出づる所の義務のみにても、之を実行することは決して容易のことではない。若し真面目に之を遂行せんとせば、終に不可能の歎きに帰するより外なきことである。私は此の不可能につき当りて、非常なる苦しみを致しました。若し此の如き不可能のことの為に、どこまでも苦しまねばならぬならば、私はとっくに自殺もとげたでありませう。然るに、私は宗教によりて、此の苦しみを脱し、今に自殺の必要を感じませぬ。私は無限大悲の如来を信ずることによりて、今日の安楽と平穏とを得て居ることであります。】 (『我が信念』)
大空

